シャンパーニュ メゾン ローラン・ペリエの象徴的な作品であり、その最高峰『ローラン・ペリエ グラン シエクル』。それが、長期の熟成を経たことで、さらなる表現を獲得した『ローラン・ペリエ レ レゼルブ グラン シエクル』として登場したのは、ローラン・ペリエ創立200周年を祝う2012年のことだった。それから12年。まさかの第2弾『ローラン・ペリエ レ レゼルブ グラン シエクル No.20』がリリースされることになった。一体なぜ? ローラン・ペリエ グラン シエクルのグローバルダイレクター エドゥアルド・コッシーさんとともに試飲しながら、この特別中の特別なシャンパーニュを考える。

久しぶりのシャンパーニュらしいシャンパーニュ
カーテン越しの朝の光を感じてウトウトしていると、窓からちょっと肌寒い風にのって、ほんのりとパンのいい香りがしてくる。耳には心地よいフルートの調べが聞こえている……
そんな紋切り型なイメージが浮かんで来て、自分に呆れている私は、口の中に、キラキラした酸味とややザラッとした硬質なものを感じているのだけれど、それがあまりにも心地よくて「なんてシャンパーニュらしいシャンパーニュだ」と言ったら目の前の男性は困ったような顔をした。
その男性はエドゥアルド・コッシーさんといい『ローラン・ペリエ グラン シエクル』のグローバルダイレクターだという。彼は、今回『グラン シエクル』を紹介するにあたって、まず『ローラン・ペリエ ブリュット ミレジメ 2012』を私に試飲させてくれた。

2012年のブドウだけで造ったシャンパーニュ。2012年の評価はやや揺れがあるけれど、私は良い年だとおもっていて、ローラン・ペリエのようなビッグネームが優良年にしか造らないブリュット ミレジメを2012年のブドウで造ったという事実は私の意見を支持してもらったようで嬉しい。
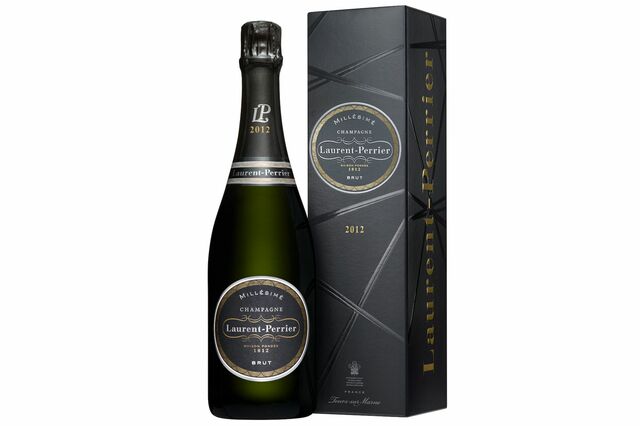
参考価格 14,530円(税別)
と、同時に、ちょっと懐かしいおもいもあった。シャンパーニュらしいシャンパーニュと言ったのは、最近、こういうシャンパーニュになかなか出会わなくなったと感じていたからだ。ここ10年くらいのシャンパーニュには、もう少しふくよかな、昼間の雰囲気を感じることが多い。温暖化にまつわる天候の変化が原因と言われがちだけれど、それは本当に気候の変化だけが理由なのだろうか? シャンパーニュの新しい表現方法が生まれつつあるのではないか? そんなもやもやしたおもいを私はこの数年抱えている。そして、それを悪いとは言いたくない。しかし、これがもし不可逆的な変化で、私がイメージするシャンパーニュらしいシャンパーニュが失われてゆくのだとしたら、私は哀惜の念に堪えない。
「たしかに、気候は変わっていて、果実は熟しやすくなっています。香りも変わりますし、ワインは重たくなる。スタイルが変化する可能性は高いとおもいます。それは悪い側面ばかりではないですから、たとえば今後、ヴィンテージシャンパーニュは増えてくるのではないでしょうか。しかし、それらのうちには、熟成能力が高くないものも少なからずあるのではないかと懸念もします」
コッシーさんはそんな風に評価したあと、ローラン・ペリエについて話してくれた。
「1948年がローラン・ペリエの第二のスタート地点、あるいは再定義された年です。ベルナール ドゥ ノナンクールがメゾンを引き継いた年。そこからベルナールが改革していった。それ以降、ローラン・ペリエはノナンクール家による一族経営の企業であり続け、ベルナールの理想を引き継いでいます」
その理想は3つの単語に集約できる、とコッシーさんは続ける。
「フレッシュネス、ピュア、エレガンス。フレッシュネスは、分かりやすい味覚で言えば酸味ですが、いまは若々しさとして表現されています。しかしこれはエネルギーです。このエネルギーが、熟成の力なのです」
では、今後もローラン・ペリエにはこのスタイルを期待していいのか? とやや前のめりになる私に、コッシーさんは、まぁそう焦らずに本題のグラン シエクルを試してみようではないか、と持ちかけるのだった。
グラン シエクル=偉大な世紀
グラン シエクルはGRAND SIÈCLEと綴り、訳せば「偉大な世紀」となる。今にしておもえばレトロスペクティブな名称である。最初のグラン シエクルは1959年、現代ローラン・ペリエの祖、ベルナール ドゥ ノナンクールが生み出した。
シャンパーニュには、他のワイン産地にはあまり見られない独特なワイン造りの方法がいくつかある。そのうちのひとつが、複数の収穫年のブドウをブレンドする、という造り方。これは、シャンパーニュ地方が寒冷ゆえ、単一年のブドウだけでは、バランスがいいワインが造れない場合に、保存しておいた過去のワインで不足を補おうという発想からそもそもは生まれている(はず)。十分によいブドウが安定的に収穫できるならば、わざわざ過去のワインの助けを借りる必要はないといえばない。ビジネス的にもその年のブドウでその年のワインを造っていったほうが、効率がいい。
しかし、そもそものところはどうあれ、こういう手法がとれるのであれば、単一年で十分に勝負できる品質のブドウ(ワイン)を、あえてブレンドすれば、一般的なワインでは到達しえない高みを目指せるのではないか? と考える人もいて、ベルナール ドゥ ノナンクールはその一人。具体的には1955年、1953年、1952年のブドウから造られたワインをブレンドすることで、優良を越えたスーパー シャンパーニュを生み出したのだ。
グラン シエクルと命名されたその作品の成功が、ローラン・ペリエの名声をシャンパーニュ最高峰の一角にまで高めたといっても過言ではないはずで、現在までに26回、グラン シエクルは生み出され、私は、グラン シエクルほど、ローラン・ペリエらしさが感じられる作品はないと感じている。
最新の26番目のグラン シエクルは2012年のワインを中核に、 2008年、2007年がブレンドされているのだけれど、続いてグラスに注がれたのはその一つ前、25番目のグラン シエクルだった。

カタログ価格 31,030円(税別)
シャルドネ約60%、ピノ・ノワール約40%のバランスでグラン・クリュの厳選されたブドウのみを使う。ちなみにグラン シエクル(偉大な世紀)とはルイ14世時代を指している。ロゴマークも太陽王のイメージ
「No.26に使われている2012年のブドウと、先にお試しいただいた『ブリュット ミレジメ 2012』のブドウは違うものなのですが、2012年よりひとつ前の優良な年は、ローラン・ペリエにとっては2008年。4年もの空白期間があります」
「つまりNo.25は、2008年が中核。そこに2007年と2006年がブレンドされています」
コッシーさんは、ちょっと試すような表情で私を見た。それがまずはひとつの回答だということなのだろう。納得がいかなければ、納得のいくブドウができるまで、4年でも待つ。良いとおもえば、2008、2007、2006年と毎年でも構わない。
「私たちは家族経営の小さな組織、日本的に言えば中小企業ですから」
規模の話でいえばローラン・ペリエはシャンパーニュの中では十分に大きいので、謙遜も混じっているとはおもうけれど、少なくとも、ブリュット ミレジメやグラン シエクルといったシャンパーニュは少量生産。量的拡大とは無縁だ。スタイルを変えてまで、無理やり毎年新作を出す意味はない、ということだろう。つまり、このスタイルを今後も期待していいのだ。
ボトルとマグナム
安心してNo.25を味わうと、その印象は鮮烈で、先の「ブリュット ミレジメ 2012」よりも若く感じるほどだった。
「これが、グラン シエクルの熟成を可能にするエネルギーです」
No.25のエネルギーというのは、パワーとか筋力とかいったものとは真逆で、ひやっとするほどの繊細さと、底の知れない含みとして感じられた。計り知れない知性と感受性の持ち主の眼差しのようだ。
「緊張感があるでしょう?」
コッシーさんはそう言う。
「これは、ブテイユです。750mlのボトル、という意味です。このほかに、倍の容量のマグナムがあります。マグナムは熟成がゆっくり進むから、まだ、熟成中でリリース前です。つまり、グラン シエクルは、No.の違いと、ボトルかマグナムかの違いがあるんです。次はマグナムで用意しました」
といって、グランスに注がれたのはNo. 23のマグナム。使われているブドウは、2006年を中核に2004年、2002年。私が大好きなシャンパーニュの収穫年の共演だ。ワクワクする。

ゆっくり味わってみると……
「あれ? 全然違いますね」
そう言った私にコッシーさんが微笑を浮かべる。それで全然違うは言い過ぎたと反省した。No.25と比べて、こちらのほうが快活ではあるけれど、同様に、天然氷のような透明感、これだけの熟成を経てなおもシャープなエレガンスがある。しかし、こうして比べてきて明らかに異なるのは、深いコク、旨味だ。それは、このシャンパーニュが長年、澱と接触した証拠だろう。
「そう。ボトルのNo.23は7年前にリリースしたのですが、マグナムは澱とともに13年、その後、澱を取り除いて1年寝かせて2020年にリリースしています」

ここで疑問が湧き上がる。スタート地点は同じNo.23。であれば、ボトルとマグナムは、同じ道をたどって、ボトルが先行した道をマグナムは後から追いかけている、と考えて良いのだろうか?
「いえ、違います。歩む道は異なるのです。ですから、すべてのグラン シエクルにはボトルとマグナム、2つの表現があると考えてください。そして、これから紹介するのが、第3の表現です」
レ レゼルブ グラン シエクル
グラスに最後のシャンパーニュが注がれた。これは『ローラン・ペリエ レ レゼルブ グラン シエクル No.20 』という。まず言いたいのは、これが輸入元・サントリーのカタログで38万円(税別)だということだ。シャンパーニュ界、いや、ワイン界の最高級品の一つである。それが飲めるというだけで、私は高揚していた。

アヴィズ、クラマン、オジェ、メニル・シュル・オジェのシャルドネが54%、アンボネイ、ブジー、トール・シュル・マルヌ、マイィのピノ・ノワールが46%というブレンド。ヴィンテージは1999年が60%、1997年と1996年が20%ずつ
「私たちはいたずらに値段を吊り上げたいわけではないんです。本数の少なさと需要から、こういう価格になる、ということはご理解ください」
そのコッシーさんの発言で冷静になった。なにやかにやと業界に長居している私の経験上、コッシーさんのこの発言は事実だ。おそらくこのシャンパーニュは、多く見積もっても世界に1,000本も存在しないだろう。そういうものは売れようが売れまいが、ワイナリーのビジネスにさしたるインパクトはないのだ。いや、扱いの面倒さから考えれば、経済面では売る理由はないに等しいリスキーな商品かもしれない。ローラン・ペリエのもっともスタンダードな『ラ・キュヴェ』の参考価格は8,030円(税別)。こちらを50本売るほうが、よほど楽なはずだ。
ローラン・ペリエ レ レゼルブ グラン シエクルは、2012年に一度発売されている。これはローラン・ペリエがごく少量、セラーに持っていたグラン シエクル No.17のマグナムを、創業200周年の記念としてリリースしたというものだった。そういう特別な記念品としてならまだしも、特にアニバーサリー・イヤーでもない2024年、12年ぶりに、なんでわざわざ、今度はNo.20のグラン シエクルにレ レゼルブの名前をつけて蒸し返すのか? 当初の高揚と打って変わって、さまざまな疑問に支配されながら、1999年、1997年、1996年という、懐かしき20世紀のブドウから生み出されたワインを口にする。そして、3回驚いた。
1. 強烈な酸味
酸味の印象だけ取ると、これが25年前のブドウだなんて信じられないほど、いきいきしている。先のフレッシュさ=エネルギーの理屈で言うと、横溢するエネルギー
2. 未体験の旨味
魚介というか、甲殻類を想起させるほどに旨味がある。シャンパーニュでここまでの旨味が出るとは、想像の遥か上を行く
3. 強烈なバランスの良さ
以上のある種じゃじゃ馬的な味覚を備えながら、甘味やスパイスの要素が感じられ、全体はバランスよくまとまっている。これひとつで料理として通用するほどだ
たしかに、これを通常のグラン シエクルと同じ線上にならべるのは、ちょっと無理がある。
なぜ今、またレ レゼルブなのか?
「最初のレ レゼルブ グラン シエクルについていえば、実は、ローラン・ペリエ内でもNo.17が良好な状態でそれなりの本数保管されていることをあまり意識していなかったのです。ベルナール ドゥ ノナンクールと醸造責任者は、グラン シエクルをある程度の本数、確保しておくことを常としてはいたのですが。そしてNo.17は、200周年という記念すべきタイミングを前にあらためテイスティングしてみると、熟成の第3段階を迎えていることが明らかでした」
そしてレ レゼルブをその一度きりのものにしてしまわなくてもよいのではないか? という発想がローラン・ペリエの中に生まれたという。
「こういうタイミングでNo.20をレ レゼルブとしてリリースしなおしたことでも想像いただけるかとおもいますが、私たちは偶然にまかせたり、何か商売上の理由からこれをリリースしたわけではありません。テイスティングして、No.20が熟成の第3段階を迎えていることを確認したので、これを、ごく限られたものとはなりますが、ローラン・ペリエを好きでいてくださる方、美食家の方に味わっていただきたいと考えてリリースしたのです」
偉大な伝統の鎖
コッシーさんと別れて、私は、19世紀フランスの詩人、ボードレールの言葉を思い出していた。イギリスに端を発した、工業化、資本主義化、民主化の波がフランスに到達したころ、絵画が変化していく様を、詩人は偉大な伝統は失われ新しいそれはまだ生まれていない、と表現した。
しかし、ボードレールは徐々に、その考えをあらためる。新しい伝統は、自分がそれと気づいていないだけで、実はすでにあるのではないか? そうして、ボードレールが探った数々の新しいものが、彼の死後、私たちが知る現代芸術へとつながっていく。ボードレールが予見したとおり、新しい伝統は生まれていたのだ。
そして、この時にボードレールが新しい伝統たりえるものとそうでないものを分ける要素としてこだわったのが、強度。失われる伝統と同じ程の強度を持っているものが、新しい伝統たりえる、という予感だった。
今、もしかしたら、シャンパーニュは、新旧の伝統の連結点にあるのかもしれない。そして、ローラン・ペリエ グラン シエクルの属しているのは、あきらかに、すでに長い歴史のある伝統の側だ。この伝統は、新しい伝統に代わられるのか、共存するのか、あるいは新しい伝統などはないのかは、今はまだ分からない。ただ、私は、この高みと並び立つ新しいシャンパーニュに出会いたい。そしてその上で、私はグラン シエクルのようなシャンパーニュが好きだ、と言いたい。


